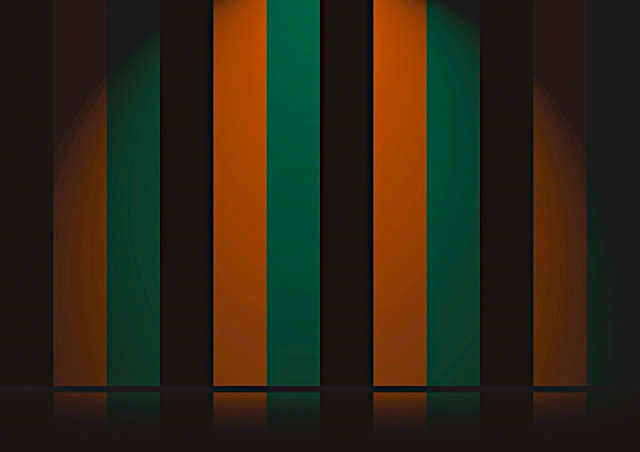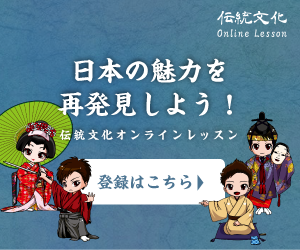学生時代は落語研究会におりました、くろーるです。
落語はお年寄りの娯楽というのは、今は昔。
お笑い好きだけではなく、言葉の勉強にもなるとアナウンサーまでが落語を聞く時代になりました。
とはいえ、子供に落語を聞かせるのは、まだまだハードルが高い・・・
落語といえば・・・

・言葉づかいが聞き慣れない
・話が長くてつまらない
・意味のわからない言葉が多数出現
大人だって聴いているのが苦痛ですからね。
でも、落語の演目は古今東西無限です!
そこで、落語研究会・通称落研(おちけん)出身の私が厳選した、子供ウケ間違いなしの演目をご紹介します!
話が短くてわかりやすい!それでいて、面白い!
子供だけではなく、落語初心者にもぜひ!!
ダジャレだから子供ウケもバツグン!口癖になる落語『 つる 』
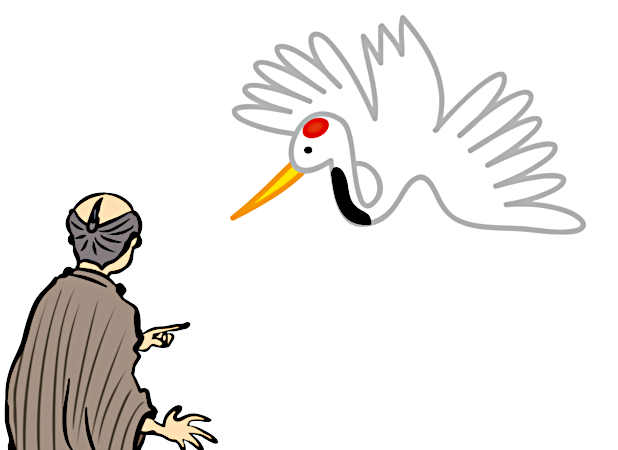
近所ではものしりとして評判のご隠居さんのところへやってきた八五郎。鶴の名前の由来を尋ねる八五郎を少しからかってやろうと思ったご隠居さんは、鶴の名前の由来だといいて作り話を教えてしまいます。ご隠居さんはシャレのつもりでしたが、八五郎はさっそく誰かの前で披露したくなって熊さんのところへ行って話始めるのですが・・・・・
| 本編時間 | 笑い度 |
| 約10分 | ★★★☆☆ |
「つる」という演目は、私の在籍していた落語研究会では1年生が演じる演目のひとつでした。
要は、演じやすい話だということです。
「登場人物の少なさ」「話の短さ」「内容の簡潔さ」と、わかりやすい要素が盛り込まれています。
笑うために見る・聴く落語として、初めてでもすぐに楽しめる演目といえるでしょう。
ココがみどころ!!
ご隠居さんがいう鶴の名前の由来とは「“つ~”と鳴いて飛んできた鳥と、“る~”と鳴いて飛んできた鳥が、ひとつの木に一緒に留まったので“つる”なんだ」。
そうです、単なるダジャレです。
話の中でオチができているところもオモシロポイントになっています。
大人も子供も、おもわず言わずにいられない・マネしたてみたいと思わせる、クセになる演目なんですね。
子供ウケ間違いなしの演目です。
私は桂歌丸師匠の軽快な口調の「つる」をおすすめします。
あなたは本当の意味を知って読み聞かせしていますか?落語『 桃太郎 』

子供を寝かしつけようと昔話「桃太郎」を聞かせてやるお父さん。ところが、聞いていた子供から、桃太郎とはそんな単純な話ではないといわれます。子供が語る「昔話・桃太郎」に隠された知られざる教訓とは??
| 本編時間 | 笑い度 |
| 約10分 | ★★★☆☆ |
「桃太郎」といえば、子供からお年寄りまで誰もが知っている昔話のド定番ですよね。
でも、この演目で犬や猿やキジ、ましては鬼が出てくることはありません。
登場人物は、お父さんと子供だけ。
見ているものにとって、登場人物が少ないことは理解がしやすいことにつながります。
昔話「桃太郎」を語って、父親らしく子供を寝かしつけようというのが本筋です。
ところが、逆に子供に知識マウントをとられるという、ありがちなオチ。
ココがみどころ!!
子供にとっては馴染み深い演目であることで、一気に興味もそそられるでしょう。
この桃太郎の話は、大人でもタメになるストーリーになっています。
中国の故事などを引き合いに語る子供に、自分もおもわずうなずいているはずです。
聴いているだけでも勉強になる気分にさせてくれますよ!
急がば回らにゃ短気は損気!落語『 長短 』

気が短くて早口の短七と気が長くてゆっくりの長さん。性格は正反対ですが、二人は馬が合うのか、今日も世間話をしています。話をしているうちに、長さんが何かを言おうとしていることに気づいた短七。長さんは言えば怒られるからといってなかなか言い出しません。怒らないから早く言うように短七は長さんを急かします。やっと話始めた長さんの言いたかったこととは?
| 本編時間 | 笑い度 |
| 約15分 | ★★★☆☆ |
“短気は損気”といって、昔から短気な人は損をするなんていいます。
といっても、早いことが最重要のIT時代にあっては、のんびり事を構える方が勝機を失いそうです。
短気の短七と気の長い長さんが登場する落語「長短」では、どちらが損をするのでしょうか?
ここに出てくる長さんは、戦場カメラマン・渡部陽一もびっくりするほどのんびりとしゃべります。
一方で、生粋の江戸っ子の短七がまくしたてる江戸弁。
“のんびり”長さんと“早口”短七のふたりの掛け合いが、なんとも笑いを誘います。
ココがみどころ!!
長さんののんびりした会話にイラついたがために犯してしまう短七のミスが途中で発生します。
オチへつながる重要な場面なのですが、見ているあなたはそれに気づけるでしょうか?
演者の演じ方によっては、あえて気づかせないこともありますので、見逃さないようにすると面白さが倍増しますよ!
15分もあるとは思えないコンパクトにまとまった演目ですので、お子さんや落語を初めて見る人でもあっという間に感じることでしょう。
情熱愛とサスペンス!どちらの解釈がお好き?落語『 千早振る 』

近所ではものしりといわれるご隠居さん。百人一首の歌人・在原業平の歌の意味を教えて欲しいと男がやってきます。ところが、ご隠居さんも歌の意味は知りません。知らないとはいえないご隠居さんは、アドリブで相撲取りが花魁(おいらん)にフラれるストーリーにしてしまったのです。無茶なストーリーだったためか、最後に歌の文字が残ってしまいます。窮地に立たされたご隠居さんの起死回生の答えとは?
| 本編時間 | 笑い度 |
| 約15分 | ★★★★☆ |
百人一首の競技カルタにかける高校生たちの物語、漫画「ちはやふる」。
平安時代のプレイボーイ・在原業平(ありわらのなりひら)の詠んだ有名な和歌の句頭を題名にしています。

簡単に、どんな歌かを解説しますね!
ちはやふる 神代もきかぬ 龍田川 からくれなゐに 水くくるとは(百人一首17番・在原業平朝臣)
【訳】神の時代でも聞いたことがなかったであろう。龍田川を紅く埋め尽くした紅葉が水をくぐる美しい様子を。
“ちはやふる~”とは、在原業平がお相手の女性に情熱的な愛を送った歌です。
百人一首にはたくさんの恋愛歌が詠まれていて、その代表作でもあります。
ところが、そうとは知らないご隠居さんの語る「ちはやふる」は、韓国ドラマも驚きのサスペンスラブストーリーになります。
元の歌を知っていればいるほど、意味のギャップに悶絶すること間違いなし。
知らなくとも、十分に面白い落語ですけどね。
そうゆう私も“ちはやふる~”の元歌は知らずに、落語「千早振る」をきっかけに百人一首に興味をもった人です。
安心して、まずは笑ってくださいね。
見た目に騙されると解けない数学問題の典型!落語『 壺算(つぼざん) 』

奥さんに水甕(みずがめ)の買物を頼まれた男は、交渉上手の源さんを連れていくようにいわれます。店の主人の前で源さんの冴え渡る交渉術。一度は、安くなった水甕を買ったものの、本当は倍の大きさの水甕が欲しいと男が言い出します。大きい水甕をさらに安く買うため、源さんが生み出した秘策とは?
| 本編時間 | 笑い度 |
| 約15分 | ★★★★☆ |
算数の授業で“つるかめ算”とか“植木算”とかを習ったことを覚えていますか?
ものを早く計算するための代表的な速算式です。
それに比べて“壺算”は、相手の計算する頭脳をマヒさせる「迷算式」。
話の筋は通っているけど、計算は合わないという迷宮のような計算をさせられます。
本当のポイントは計算式ではなく、「下取り」か「返品」かってところなんですけどね。
店の主人もおそらく会計には弱いと見えます。
数学の入試問題でも、見せかけと問いの狙いが違うものってよくあります。
聞いてる方も、ちょっと油断をすると源さんの計算が合っている気がしてくるからご用心!

あなたもダマされてはいけませんよ!
百人一首をリスペクトした最高のオチを聞き逃すな!落語『 崇徳院(すとくいん) 』

寝込む若旦那のところへ呼び出された熊さん。若旦那の病気の原因は、なんと“恋患い”。相手の女性を見つけたら三軒長屋(今のアパート)をくれるといわれたものの、相手が誰かもわかりません。たったひとつの手掛かりは“崇徳院様の和歌”。人の集まる江戸中の床屋と風呂屋へ行っては、崇徳院様の和歌を歌い出すなんとも迷惑な熊さん。歩き疲れて床屋で休んでいると、若旦那を探しているという男がやってきます。互いに探していた相手を見つけた二人は、床屋で押し問答に。ついには店の鏡を割ってしまった熊さんの言い訳とは?
| 本編時間 | 笑い度 |
| 約15分 | ★★★★☆ |
平安時代後期の天皇のひとりである崇徳院。
歌の詠み手としても知られており、百人一首に選ばれているこの歌も、大変情熱的な恋の歌です。

とっても情熱的な恋愛歌!百人一首が好きになってしまいますよ!
瀬をはやみ 岩にせかるる 滝川の われても末に 逢はむとぞ思ふ(百人一首77番・崇徳院)
【訳】川の早い流れが岩によって割られるように私たちも離れ離れになろうとも、川の流れも元に戻るようにいつか再び逢いたいと思います。
こんな歌を相手から送られたら、思わずグラッと心が動いてしまいますよね。
若旦那が恋患いになってしまう気持ちもわかります。
″ちはやふる~″にしても、この崇徳院の歌にしても、百人一首を恋愛歌から学んでみると興味が湧きますよ!
平安時代の人だって、恋愛のせつなさ、甘酸っぱさは変わらないのです。
話の筋は、若旦那のひと目惚れ相手を探してのドタバタですが、注目はオチです。
崇徳院の歌を用いたラストは、おそらく落語演目の中でも有数の美しいオチだと思います。
子供はみんなオナラが大好き!落語『 転失気(てんしき) 』

体調がすぐれないお寺の和尚さん。医者を呼んで診てもらったところ、「“てんしき”はありますか?」と聞かれます。知ったかぶりをして「あります。」と和尚さんは答えたものの、気になる和尚さんは、寺の小僧に同じように知ったフリをして“てんしき”を借りてくるようにいいつけます。わけもわからず“てんしき”を借りにいく小僧さんが知った“てんしき”の正体とは??
| 本編時間 | 笑い度 |
| 約15分 | ★★★★☆ |
まずは、最初にネタバレです。

転失気(てんしき)って、オナラのことだよ!
「転失気=オナラ」のことですが、いわゆる隠語になっています。
隠語とは、ある特定の人にだけ意味が伝わる隠し言葉や暗号といったところでしょうか。
和尚さんを診察した医者は、てっきり知ってものとして話したのですが、和尚さんは知らなかったわけです。
転失気を知ったふりをする大人たちが次々と登場。
転失気を食べた人や転失気を飾ってある人が出てくるのですから、クスクスせずにはいられません。

子供はみんなオナラが大好き!!
なんなら“オナラ”だけで、ずっと笑っていられます。
“てんしき”が何かがわからないまま進む前半パートに、少し飽きがあるかもしれませんが、オナラであることがわかってからの笑いの破壊力はスゴイものがあります。
10分強くらいの長さ演目ですが、下ネタ話って時間を感じさせないものですよね。
ヘン顔は怪しい人の代名詞!表情必見の落語『 にらみ返し 』
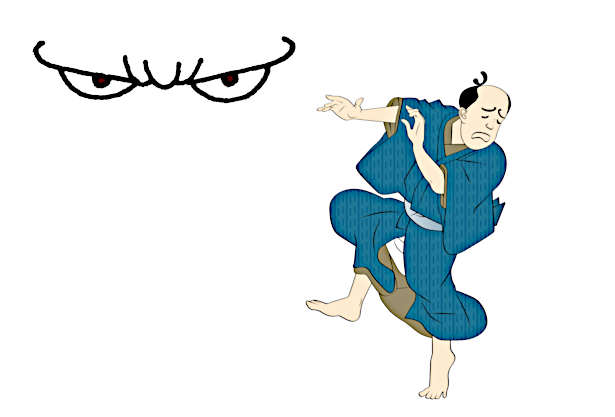
今年も残りあと少しと迫った年末。ぞくぞくと借金取りがやってくるものの、返すアテはありません。そこへ“どんな借金取りも追い返す”というプロが現れて・・・
| 本編時間 | 笑い度 |
| 約20分 | ★★★★☆ |
落語は聞かせるものが多い印象をもっているかもしれませんが、この「にらみ返し」は顔芸が最大の面白さになっている演目です。
ラジオやCDでは、その面白さが全く通じません。
だって、借金取りがやってきても一言もしゃべらず、にらんで追い返すというプロが出てるのですから。
演じてる間にも、シーンとなる場面が何度も出てきます。
ひたすら、にらみ顔が続くというカオスな世界をお楽しみください。
子供に難しい言葉や風景が一切ないことも、おすすめポイント。
ヘン顔を見て、ずっと笑っていられる落語です。
まとめに:子供ウケが悪い大ネタや名人の落語
落語好きであるほど、名人の落語や大ネタを好きな演目にあげることと思います。
確かに、芸の細かさや表現力、笑いの完成度の高さは素晴らしいものがあります。
いいものを子供にも聞かせたいという気持ちもわかります。
ただ、音源が古くて聞き取りにくかったり、江戸言葉が聞き取れないなど、子供の興味が続かない状況が生まれるのです。
むしろ、現在活躍中の落語家さんの音源を探してくるなど、聞き取りやすいものを選んで、子供に聞かせることがいいでしょう。
オンラインで手軽に落語の稽古【落語ワークショップ】は会員登録無料‼(PR)
- 気になる落語の世界を体験したい!
- 話で人を笑わせられるようになりたい
- 家の近くに落語を学べる場所がない
- 独学ではなく先生に落語を教わりたい
- 面白い話をする技術を身につけたい
- 自分の一芸として落語を覚えたい
- 落語の小噺をたくさん覚えたい
ひとつでも当てはまるなら、落語ワークショップをご体験ください。
講師歴50年以上の笑生十八番(しょうせい おはこ)先生の指導により、ZOOMを利用して行います。
台本も用意をしてくれて、基本から丁寧に教えてもらえるので、気軽に稽古を受けてくださいね!