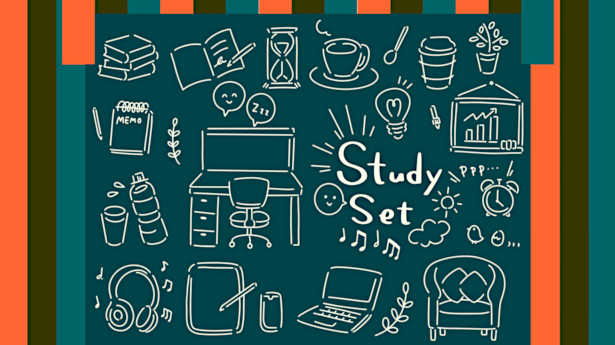学生時代は落語研究会におりました、くろーるです。
漫才やコントなどと並びお笑い演芸のひとつでもある落語。
面白おかしいことをするわけですが、意外にも高尚な演目もあるのです。
笑っているうちに、あなたのIQが試されているとしたら?

この落語、あなたには理解できますか?
笑いについていけなかったら、すぐに勉強をしてください。
思わず勉強せずにはいられない、笑えてタメになる演目をご紹介します!!
数字のマジックにダマされるな!「数学・算数系落語」
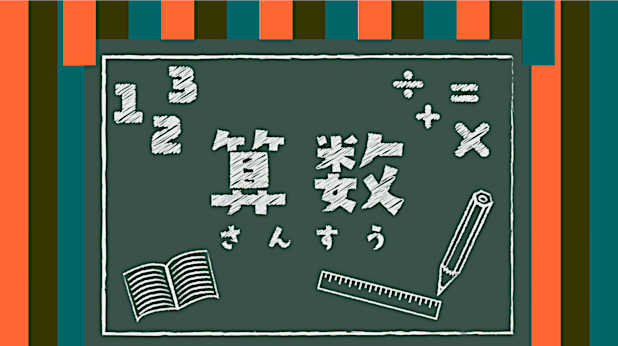
落語と数学・算数って対極にあるような気がしますよね。
ところが、案外、落語に出てくるようなヤツらのように、物事を柔らかくナナメから見るような考え方が必要かもしれませんよ。
見た目に騙されると解けない数学問いの典型!落語「壺算(つぼざん)」

奥さんに水甕(みずがめ)の買物を頼まれた男は、交渉上手の源さんを連れていくようにいわれます。店の主人の前で源さんの冴え渡る交渉術。一度は、安くなった水甕を買ったものの、本当は倍の大きさの水甕が欲しいと男が言い出します。大きい水甕をさらに安く買うため、源さんが生み出した秘策とは?
算数の授業で“つるかめ算”とか“植木算”とかを習ったことを覚えていますか?
ものを早く計算するための代表的な速算式です。
それに比べて“壺算”は、相手の計算する頭脳をマヒさせる「迷算式」。
話の筋は通っているけど、計算は合わないという迷宮のような計算をさせられます。
本当のポイントは計算式ではなく、「下取り」か「返品」かってところなんですけどね。
店の主人もおそらく会計には弱いと見えます。
数学の入試問題でも、見せかけと問いの狙いが違うものってよくあります。
聞いてる方も、ちょっと油断をすると源さんの計算が合っている気がしてくるからご用心!

あなたもダマされてはいけませんよ!
単位が違うことを利用したテクニック!落語「時そば」
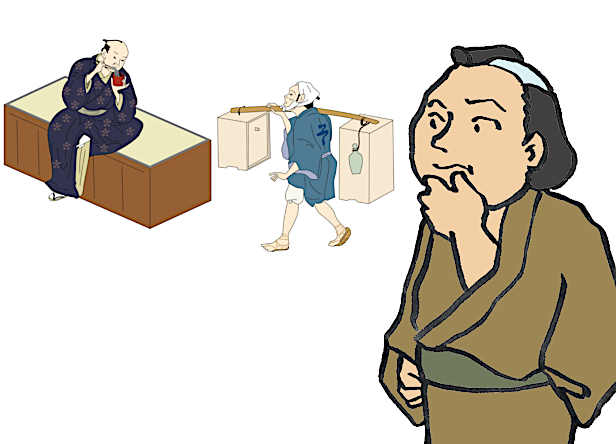
ある寒い夜。そばの屋台先でそば屋の主人を褒めながら、そばを食べていった男がいました。なんと、その男は、うまくそば屋の主人をおだてて、そば代をごまかして帰っていったのです。その様子を見ていた男が、自分もあの男のマネをすれば、安くそばを食べられると考えます。ところが、別のそば屋台で、あの男と同じようにいうものの、なかなかうまくいきません。いよいよ、そば代を支払うことになるのですが・・・・・
落語の演目の中でも有名な「時そば」の中に出てくる男は、まさに詐欺師!
では、そのテクニックはどこが上手なのでしょう?
それは、単位の違い!
そばの代金は小銭の数、そして、途中でこの男がそば屋台の主人に聞く質問は時間です。
聞いた言葉は同じでも、その価値の単位が違うところにダマしのテクニックが隠れているのです。
数字はものごとを明確にさせることができる利点があります。
その一方で、単純化できることを悪用することもできることを、この男は知っていたのです。
また、時そばで使われたテクニックは、一度に多くの情報を与えることで、脳が処理できなくなる状況を作り出すという詐欺の手法のひとつも用いています。

詐欺を思いつく人って、その頭脳を良いことに使えばいいのにって思いませんか?
もっとも、マネをしようした男は、うまくいかずにむしろそばの代金を多く払うことになるのですが。
いい和歌ほど遊びがいがある!百人一首が身につく「国語系落語」
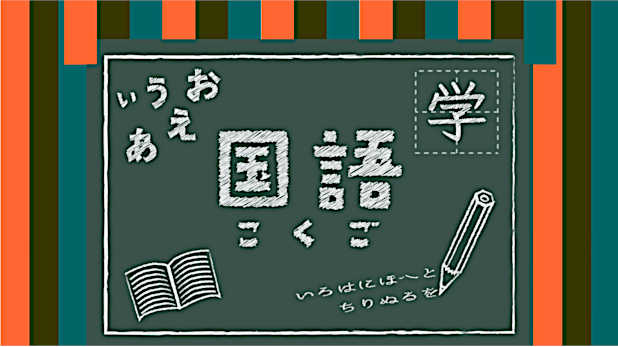
国語において古典を苦手にしている人も多くいます。
古典には、慣れ親しむのが一番の勉強法です。
面白おかしく和歌の世界に触れてみるのもいいかもしれませんよ!
情熱愛とサスペンス!どちらの解釈がお好き?落語「千早振る(ちはやふる)」

近所ではものしりといわれるご隠居さん。百人一首の歌人・在原業平の歌の意味を教えて欲しいと男がやってきます。ところが、ご隠居さんも歌の意味は知りません。知らないとはいえないご隠居さんは、アドリブで相撲取りが花魁(おいらん)にフラれるストーリーにしてしまったのです。無茶なストーリーだったためか、最後に歌の文字が残ってしまい、窮地に立たされたご隠居さんの起死回生の答えとは?
百人一首の競技カルタにかける高校生たちの物語、漫画「ちはやふる」。
平安時代のプレイボーイ・在原業平(ありわらのなりひら)の詠んだ有名な和歌の句頭を題名にしています。

簡単に、どんな歌かを解説しますね!
ちはやふる 神代もきかぬ 龍田川 からくれなゐに 水くくるとは(百人一首17番・在原業平朝臣)
【訳】神の時代でも聞いたことがなかったであろう。龍田川を紅く埋め尽くした紅葉が水をくぐる美しい様子を。
“ちはやふる~”とは、在原業平がお相手の女性に情熱的な愛を送った歌です。
百人一首にはたくさんの恋愛歌が詠まれていて、その代表作でもあります。
ところが、そうとは知らないご隠居さんの語る「ちはやふる」は、韓国ドラマも驚きのサスペンスラブストーリーになります。
元の歌を知っていればいるほど、意味のギャップに悶絶すること間違いなし。
知らなくとも、十分に面白い落語ですけどね。
そうゆう私も“ちはやふる~”の元歌は知らずに、落語「千早振る」をきっかけに百人一首に興味をもった人です。
安心して、まずは笑ってくださいね。
百人一首をリスペクトした最高のオチを聞き逃すな!落語「崇徳院(すとくいん)」

寝込む若旦那のところへ呼び出された熊さん。若旦那の病気の原因は、なんと“恋患い”。相手の女性を見つけたら三軒長屋(今のアパート)をくれるといわれたものの、相手が誰かもわかりません。たったひとつの手掛かりは“崇徳院様の和歌”。人の集まる江戸中の床屋と風呂屋へ行っては、崇徳院様の和歌を歌い出すなんとも迷惑な熊さん。歩き疲れて床屋で休んでいると、若旦那を探しているという男がやってきます。互いに探していた相手を見つけた二人は、床屋で押し問答に。ついには店の鏡を割ってしまった熊さんの言い訳とは?
平安時代後期の天皇のひとりである崇徳院。
歌の詠み手としても知られており、百人一首に選ばれているこの歌も、大変情熱的な恋の歌です。

とっても情熱的な恋愛歌!百人一首が好きになってしまいますよ!
瀬をはやみ 岩にせかるる 滝川の われても末に 逢はむとぞ思ふ(百人一首77番・崇徳院)
【訳】川の早い流れが岩によって割られるように私たちも離れ離れになろうとも、川の流れも元に戻るようにいつか再び逢いたいと思います。
こんな歌を相手から送られたら、思わずグラッと心が動いてしまいますよね。
若旦那が恋患いになってしまう気持ちもわかります。
″ちはやふる~″にしても、この崇徳院の歌にしても、百人一首を恋愛歌から学んでみると興味が湧きますよ!
平安時代の人だって、恋愛のせつなさ、甘酸っぱさは変わらないのです。
話の筋は、若旦那のひと目惚れ相手を探してのドタバタですが、注目はオチです。
崇徳院の歌を用いたラストは、おそらく落語演目の中でも有数の美しいオチだと思います。
歴史の偉人の功績を学ぶ「社会系落語」
江戸の名工・左甚五郎はヒーローだった!?落語「ねずみ」
客引きの子供に誘われるまま貧乏宿屋「鼠(ねずみ)屋」へ泊ることとなった旅人。父子でやっているとはいえ、そのあまりの粗末さに宿屋のいきさつを聞いてみると、向かいの大宿屋「虎屋」を乗っ取られた末のことだと知ります。旅人は、ひとつのねずみを彫ると、そこに「左甚五郎」と書置きし去っていきます。その旅人とは、江戸の名工だったのです。左甚五郎に彫られたそのねずみ。不思議なことにチョロチョロと動き出したのです。評判は評判を呼び、「鼠屋」は大繁盛。それを妬んだ「虎屋」の主人は、店の屋根に木彫りの虎を置いたとたん、「鼠屋」のねずみは動かなくなってしまいます。その理由を聞いてみると・・・
「ねずみ」という落語は、江戸初期に活躍した木彫の名工・左甚五郎(ひだりじんごろう)にまつわる人情話です。
日光東照宮の眠り猫や上野東照宮唐門の昇り龍・降り龍などがよく知られています。
左甚五郎の作品には伝説上の動物も含め、生き物を題材にしたものも多く残されます。
木彫りでありながら、まるで命を吹き込まれたようないきいきとした作風が見られるのです。
その演目のとおり、左甚五郎に命を吹き込まれた木彫りの「ねずみ」。
主人公であるはずの木彫りの「ねずみ」は、お客たちの目線から動く様子を描写されます。
そして、いよいよ最後に登場する木彫りの「ねずみ」の一言が、スカッとした気分にさせて幕を閉じます。

水戸黄門的な勧善懲悪ものになっていますよ!
人情話は、その内容上、しんみりしたシーンが多くて退屈しがちです。
そこを、左甚五郎と子供の掛け合いから、主人との話、そして野次馬の客たちのドタバタと場面展開が早く、飽きさせません。
まとめに:聞くだけで自然に知識が身につくところが落語
落語と勉強は、一見すると対極にあるような気がします。
しかし、意外にも笑いの中に、うまく知識を入れ込んでいるネタはたくさんあります。
ここでご紹介した演目の他にも多くありますが、その中でも笑える楽しいネタを選んでいます。
もちろん、何も知らなくても十分笑えますが、ベースの知識を知っているほど面白さは増すはずです。
気に入ったネタがあったら、そのネタの背景やわからない点を勉強すると、知識は深まり面白さも倍増!

これぞ!勉強系落語の醍醐味!!